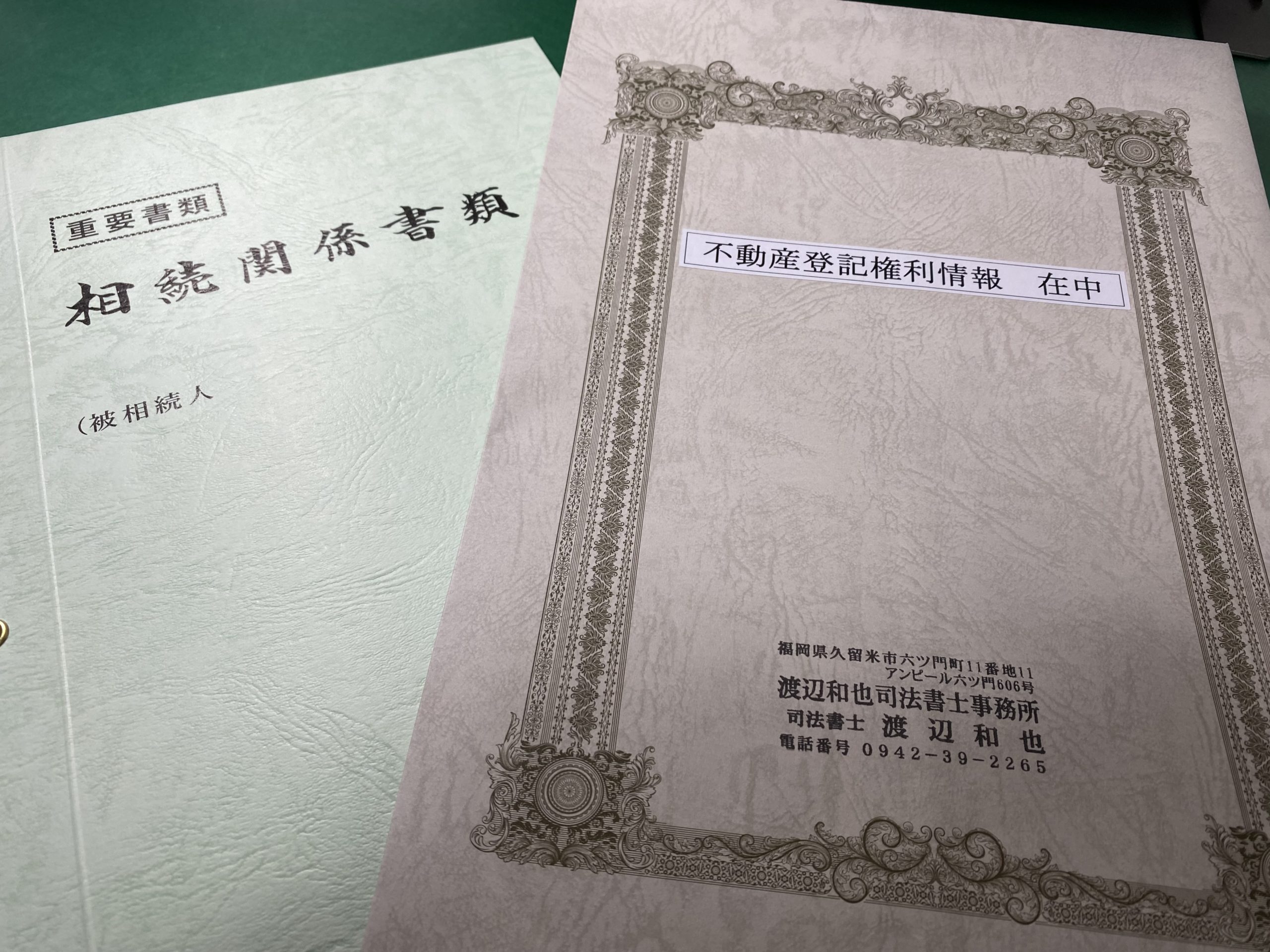包括遺贈とは・・・遺産の全部あるいは何分の1という形でされるもの(有斐閣「法律学小辞典」)です。
民法(抜粋)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
そして、包括遺贈には相続人に関する規定が適用されます。
民法(抜粋)
第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
包括受遺者に相続人の権利義務に関する規定が適用される結果、民法第915条(相続放棄の規定)は、
民法(抜粋・当サイトによる読み替え後)
第九百十五条 包括受遺者は、自己のために包括遺贈があったことを知った時から三箇月以内に、包括遺贈について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
第九百三十八条 包括遺贈の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
のようになります。
そして、遺贈は、推定相続人ではない人に対してもすることができます(実務的には、むしろ相続人に遺贈することの方が稀ではないかと思います。)。
したがって、”包括”遺贈の場合は、相続人ではない人が家庭裁判所において相続放棄の申述と同様の手続(包括遺贈放棄の申述)を行うケースがありえるということになります。
包括遺贈は遺言者の遺産を割合的に引き継ぐ遺贈ですので、その包括受遺者が遺言者の相続人ではなかったとしても、債務があればその債務も含めて遺産の当該割合を引き継ぐことになります。債務を引き継ぎたくない場合やプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などは、相続放棄と同じように、家庭裁判所で包括遺贈放棄の申述をした方がよいケースと言えます。なお、包括遺贈を放棄をした人は、初めから包括受遺者とならなかったものとみなされます(民法第990条、同第939条)。
ちなみに、特定遺贈(特定の財産に対してされるもの。財産が特定・独立のものである限り、直ちに権利移転を生ずると解される(有斐閣「法律学小辞典」)の場合は、遺言者の死亡後、いつでも放棄することができます(民法第986条第1項)。家庭裁判所やその他の公的機関で相続放棄の申述のような手続をする必要はなく、遺贈義務者(遺言執行者・遺言執行者がいなければ相続人)に対して遺贈を放棄する旨の意思表示をして行います。期限もありません。