公正証書遺言とは
 遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、遺言書を公正証書として作成するものです。
遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、遺言書を公正証書として作成するものです。
公正証書遺言は、最終的には公証人が作成するものですので、方式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどありません。
また、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができ、相続人の負担の軽減にもつながります。
さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
したがいまして、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて安全確実な遺言方法であると言えます。
こちら もご参照ください。
日本公証人連合会のウェブサイトの 遺言のページ
作成日当日に必要となる書類等
- 印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの) ※返却されません。
- 実印
- 顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証など)
- 相続させる場合は、遺言者と推定相続人との関係が分かる戸籍謄本
配偶者に相続させる場合・・・遺言者の戸籍謄本 子に相続させる場合・・・子が一緒に記載されている遺言者の戸籍謄本(改製前の縦書きの戸籍謄本でも可)、又は父母欄に氏名が記載されている子の各々の戸籍謄本
兄弟姉妹に相続させる場合・・・遺言者の親の戸籍謄本で子供が記載(除籍されていても可)されている戸籍謄本(改製前の縦書きの戸籍謄本でも可)、又は父母欄に氏名が記載されており親が同じであることが分かる兄弟の各々の戸籍謄本
- 相続人以外の人に財産をあげる(遺贈する)場合は、財産をもらう人(受遺者)の住民票
- 財産の中に不動産がある場合は、固定資産評価証明書(名寄帳でも可)又は固定資産税の課税明細書と登記事項証明書(登記情報提供サービスの登記情報でも可)
- 財産の中に預貯金がある場合は、預貯金通帳の写し又は金額を記載したメモ(手書き可)
- 財産の中に有価証券(株式、投資信託など)がある場合は、証券会社発行の取引明細書など
業務の流れ
- ご依頼者様のご自宅などご指定の場所にお伺いする日時を調整させていただきます。
- オンライン面談の場合は、ZoomのURL等のご案内をいたします。
- ご依頼者様のご本人確認をさせていただきます。
- 業務依頼書にご署名いただきます。
- 親族関係(推定相続人)などをお聴きします。
- 遺言の内容(ご意向)などをお聴きします。
- 財産関係の書類をお預かりする場合があります。
- 相続させる推定相続人が直系尊属又は兄弟姉妹である場合は、必ずご依頼者様(遺言者)の子の有無について戸籍を遡って調査させていただきます。その他の場合でもご希望により必要な戸籍を当事務所で取得することが可能です。
- お聴きした内容のとおりの遺言の原案を作成します。
- 完成後、内容を確認していただきます。
- 何度かやりとりが必要になる場合があります。
- 原案が確定した段階で金額をご案内しますので、司法書士報酬をお振込みいただきます。
- 当事務所が公証役場と遺言内容や公正証書作成の日時の調整をします。
- 作成日当日に必要となる書類等と公証人手数料の見積額をお知らせします(作成日当日にご持参いただきます。)。
- 予定の時刻に公証役場でご依頼者様(遺言者)、当事務所司法書士を含む立会人(証人)2名が集まります。
- 公証人が原案を基に公正証書遺言を作成し、ご依頼者様(遺言者)と立会人(証人)に読み聞かせを行い、遺言書の原本に全員が証明・押印します。
- 公証役場に公証人手数料をお支払いいただきます。
料金
料金は こちらです。
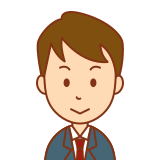
当事務所は、遺言者様のご負担が最小限となるように支援業務を行っております。お気軽にお問い合わせください。
