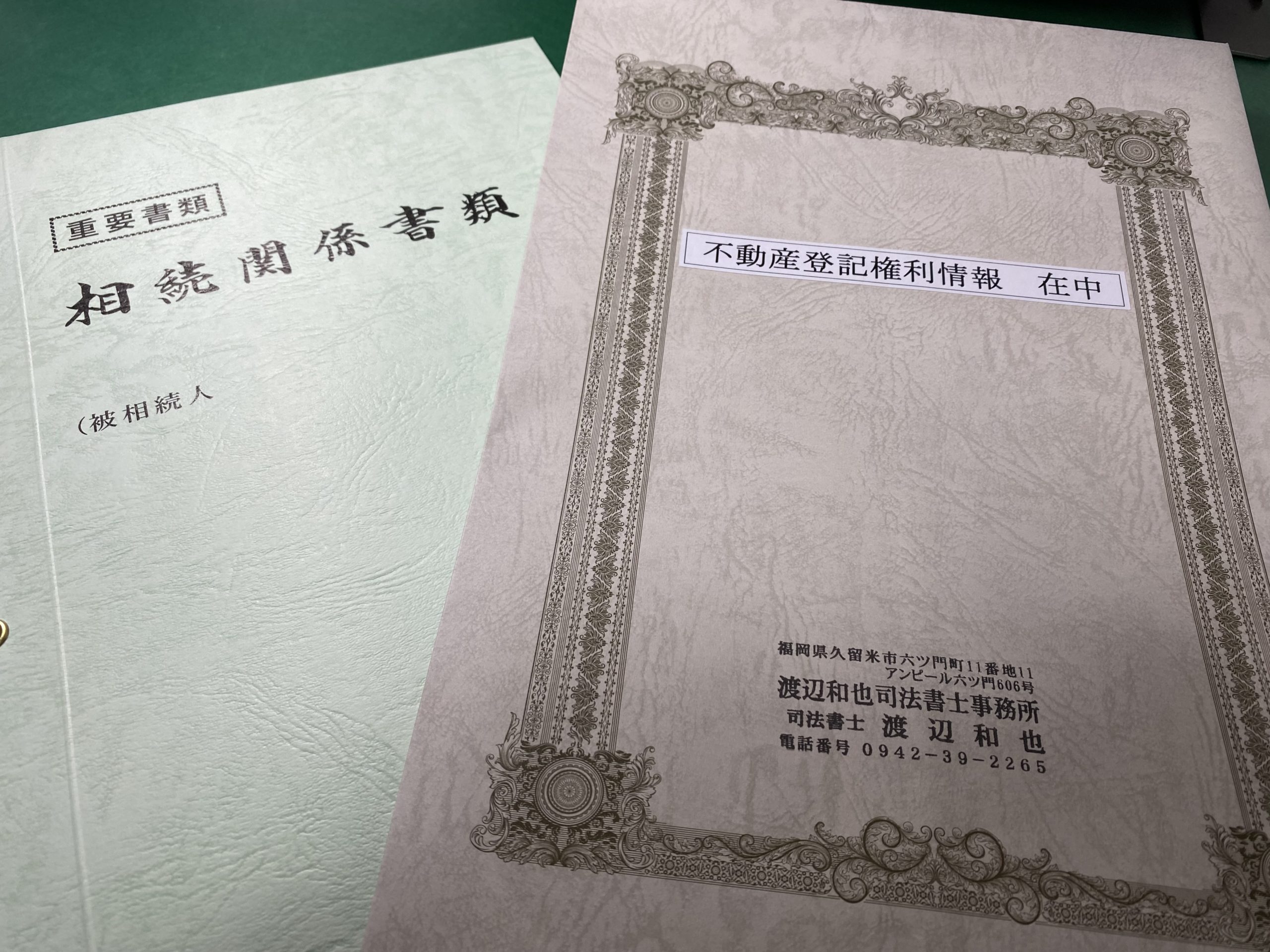※ 以下の説明は、相続人以外への遺贈の登記に関するものです。
遺贈を原因とする所有権移転登記は、遺言執行者がいる場合といない場合とで以下の違い(朱書き部分)があります。
遺言執行者がいないと登記手続に遺言者の相続人全員の関与が必要となり、場合によってはスムーズに申請することができなくなります。受遺者の負担を軽減するためにも、遺言をする際は必ず遺言執行者を指定するようにしておきたいものです。
遺言執行者がいる場合
申請人
登記権利者・・・受遺者
登記義務者・・・遺言執行者
による共同申請
遺言で受遺者が遺言執行者に指定されていれば、同一人が登記権利者・登記義務者として登記申請することができます(大正9年5月4日民第1307号通達)。→事実上の単独申請となります。
添付情報(原則)
※相続人が配偶者と子の場合です。
登記原因証明情報
遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済みのもの又は法務局の遺言書情報証明書)
遺言者の死亡事項の記載のある戸籍謄本(又は除籍謄本、改製原戸籍謄本)
遺言者の住民票の除票の写し(本籍の記載のあるもの)又は戸籍の附票の写し(本籍の記載のあるもの) ※ 遺言者の登記記録上の住所と戸籍謄本の本籍とを関連づけるためです(青山修著「不動産登記申請MEMO -権利登記編- 補訂新版」)。なお、登記記録上の住所と死亡時の住民票上の住所が異なる場合は、遺贈を原因とする所有権移転登記の前に所有権登記名義人住所変更登記を申請する必要があります(昭和43年5月7日民甲第1260号回答、登記研究380号81頁)。
※ 戸籍は法定相続情報一覧図で代用可能です。
登記識別情報又は登記済証
遺言者が当該不動産の所有権移転登記を受けた際のもの
住所証明情報
登記権利者の住民票の写し
印鑑証明書
遺言執行者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
代理権限証明情報
遺言執行者が指定されている遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済みのもの又は法務局の遺言書情報証明書) ※ 登記原因証明情報と同一なので、二重に添付する必要はありません。
遺言者の死亡事項の記載のある戸籍謄本(又は除籍謄本、原戸籍謄本) ※ 登記原因証明情報と同一なので、二重に添付する必要はありません。
その他
固定資産評価証明書、名寄帳、課税明細書などの不動産の固定資産評価額が分かる書類
遺言執行者がいない場合
申請人
登記権利者・・・受遺者
登記義務者・・・遺言者の相続人(全員)
による共同申請
添付情報(原則)
※相続人が配偶者と子の場合です。
登記原因証明情報
遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済みのもの又は法務局の遺言書情報証明書)
遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の全部
遺言者の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)の写し又は戸籍の附票の写し(本籍の記載のあるもの) ※ 遺言者の登記記録上の住所と戸籍謄本の本籍とを関連づけるためです(青山修著「不動産登記申請MEMO -権利登記編- 補訂新版」)。なお、登記記録上の住所と死亡時の住民票上の住所が異なる場合は、遺贈を原因とする所有権移転登記の前に所有権登記名義人住所変更登記を申請する必要があります(昭和43年5月7日民甲第1260号回答、登記研究380号81頁)。
相続人全員の戸籍抄本 ※ 謄本でも可
※ 戸籍は法定相続情報一覧図で代用可能です。
登記識別情報又は登記済証
遺言者が当該不動産の所有権移転登記を受けた際のもの
住所証明情報
登記権利者の住民票の写し
印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書(3か月以内のもの)
その他
固定資産評価証明書、名寄帳、課税明細書などの不動産の固定資産評価額が分かる書類
関連事項
登録免許税は1000分の20です。登記権利者が相続人の場合(「遺贈の登記の単独申請について」をご参照ください。)は、相続人であることを証する戸籍抄本又は謄本を添付することにより1000分4となります。
当事務所の業務